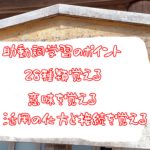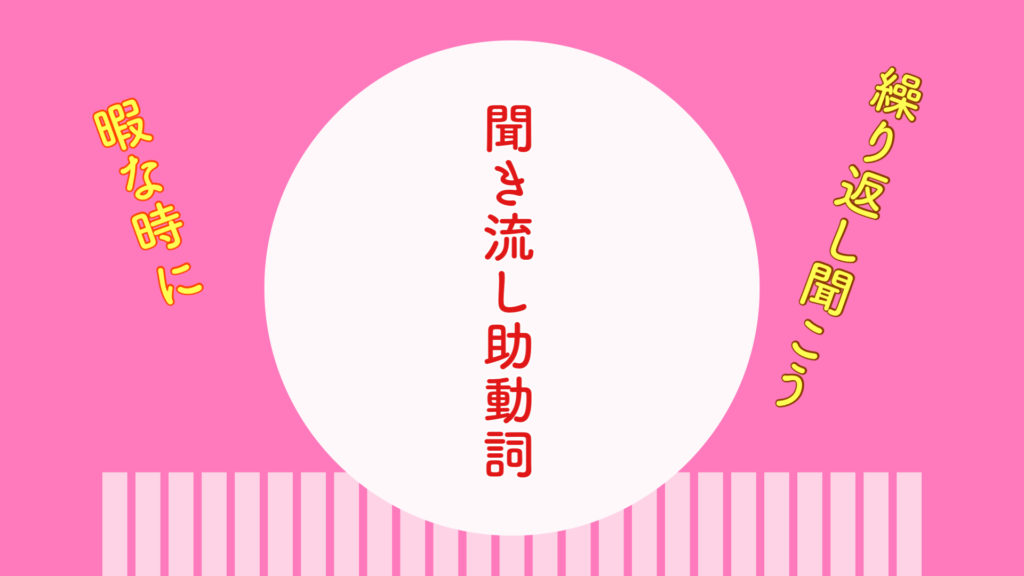朗 読
本 文
養ひ飼ふものには、馬・牛。繋ぎ苦しむる こそ いたましけれど、なくてかなはぬものなれば、いかがはせ aん。犬は、守り防ぐつとめ、人にもまさりたれば、必ずあるべし。されど、家ごとにあるものなれば、ことさらに求め飼はずともありな bん。
その外の鳥・獣、すべて用なきものなり。走る獣は檻にこめ、鎖をさされ、飛ぶ鳥は翅を切り、籠に入れられて雲を恋ひ、野山を思ふ愁へ、止む時なし。その思ひ、我が身にあたりて忍び 難くは、心あらん人、これを楽しまん や。生を苦しめて目を喜ばしむるは、桀・紂が心なり。王子猷が鳥を愛せし、林に遊ぶを見て、逍遥の友としき。捕へ苦しめたる にあらず。
およそ、「めづらしき禽、あやしき獣、国に育はず」とこそ、文にも侍るなれ。
口 語 訳
「飼うべき動物として、馬と牛がいる。繋いで苦しめるのは痛ましいが、これらがいなければ困るので仕方がない。犬は(家を)守るという役割があり、人間にも劣らない存在なので、必ず飼うべきだ。しかし、どの家でも飼われているので、わざわざ求めて飼う必要はないだろう。
その他の鳥や獣など、すべて役に立たないものだ。走る獣は檻に入れられ、鎖で繋がれ、飛ぶ鳥は羽を切られ、籠に入れられて雲を恋しがり、野山を思い悩むことが絶えない。その思いは我々自身にも当てはまり、耐え難いものだ。心ある人間が、これを楽しむことができるだろうか。生命を苦しめて目を楽しませるのは、桀と紂の心のようだ。(風流人の)王子猷は鳥を愛し、林で遊ぶのを見て、逍遥の友とした。それは捕えて苦しめることではない。
だいたい「珍しい鳥、奇妙な獣、国で育てない」と、書物にも記されている通りだ。
問題(む・むず)
問一 傍線部a・bの助動詞の文法的意味と活用形を答えよ。
問二 以下の傍線部の「む」のうち、「推量」となるものを記号で答えよ。
(1)男はこの女をこそ得めと思ふ。
(2)思はむ子を法師になしたらむこそ心苦しけれ。
(3)子といふもの、なくてありなん。
(4)心あらん人、これを楽しまんや。
問三 傍線部の助動詞の意味をあとから選び、記号で答えよ。
(1)この殿の父、討たれぬと聞いて、いかばかりか嘆き給はんずらん。
(2)もし人手にかからば自害をせんずれば、
〈 ア 推量 イ 意志 ウ 適当・勧誘 エ 仮定・婉曲 〉
問四 筆者が考える「犬」を飼うべき理由を簡潔に答えよ。
模 範 解 答
問一 a 意志 連帯形 b 推量 終止形
問二 (4)
問三 (1)ア (2)イ
問四 犬は家を守り、外敵を防ぐ働きが人よりも優れているから。