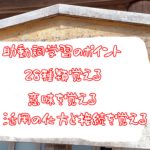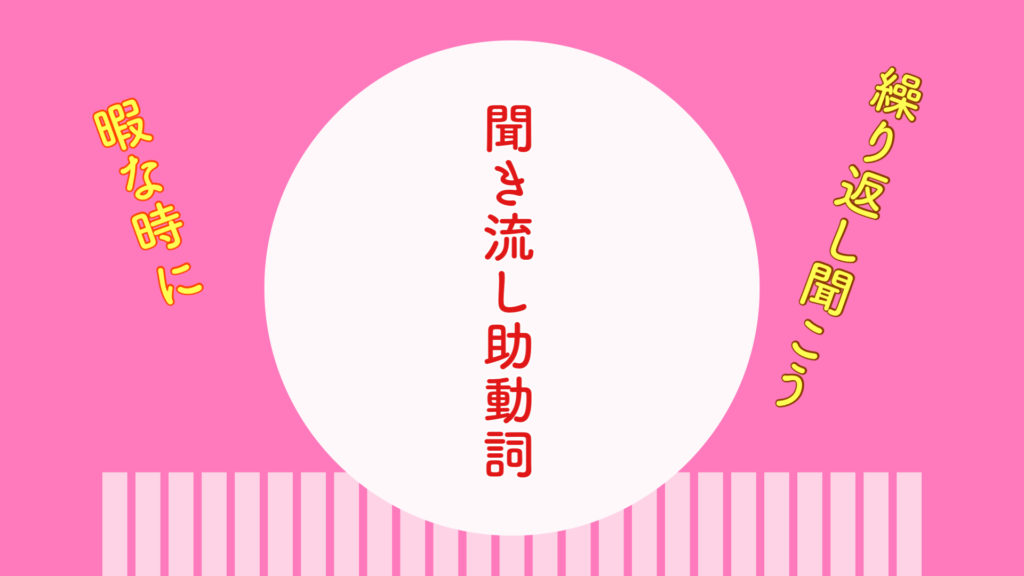朗 読
本 文
人の才能は、文 あきらかにして、聖の教えを知れるを第一とす。次には手書く事、むねとする事はなくとも、これを習ふ aべし。学問に便あらんためなり。次に医術を習ふべし。身を養ひ、人を助け、忠孝のつとめも、医にあらずはある bべから ず。次に弓射、馬に乗る事、六芸に出せり。必ずこれをうかがふべし。文・武・医の道、誠に、欠けてはあるべから ず。これを学ばんをば、いたづらなる人といふべから ず。次に、食は人の天 なり。よく味はひをととのへ知れる人、大きなる徳とすべし。次に細工、よろづに 要多し。
この外の事ども、多能は君子の恥づる処なり。詩歌にたくみに、糸竹に妙なるは幽玄の道、君臣これを重くすといへども、今の世にはこれをもちて世を治むる事、漸くおろかなるに似たり。c「金はすぐれたれども、鉄の益多きにしかざるがごとし。」
口 語 訳
人の才能は、四書五経などの古典に通じていて、古の聖人の教えを知っていることを第一とする。次は書道で、専門家を目指すわけでなくとも習っておいた方が良い。学問をする時の手助けとするためである。その次は医術だ。自身の健康管理だけでなく、人命を救い、人に尽くすのは、医術の他にない。次に、弓を射ること、馬に乗ること、六芸(りくげい。 古代中国で士以上の者が修得すべきとされた分野)に挙げられている。必ずこれを一通り学ぶべきだ。文・武・医の道は、本当に、欠けてはならないものである。これを学ぶ人を、無駄なことをする人と言ってはならない。その次に食があるが、生命にとって太陽と同じくらい重要である。料理が上手な人は、偉大な才能を授けられたと思って良い。次に手細工、あらゆることに役立つ。
この他にも様々な能力があるが、何でもこなす超人というのは恥ずべき存在でしかない。詩歌にたくみで、見事に管弦を奏でることは、優美で奥深い領域として君も臣もこれを重く考えるとはいっても、今の世にはこれらの能力で世を治めることは、だんだん不可能になってきているようだ。金はすぐれているといっても、鉄の利用価値に及ばないのと一緒である。
問 題
問一 傍線部a・bの助動詞の文法的意味と活用形を答えよ。
問二 以下の傍線部の「べし」のうち、「意志」となるものを記号で答えよ。
(1)この一矢(ひとや)に定むべし。
(2)さりぬべき折をも見て、対面すべくたばかれ。
(3)ほととぎす鳴くべき時に近づきにけり。
(4)家の作りやうは、夏をむねとすべし。
問三 以下の( )に入る「べし」を適当に活用させて答えよ。
(1)人は、形・有り様のすぐれたらんこそ、あらまほしかる(べし)。
(2)子となり給ふ(べし)人なめり。
(3)なほ、さりぬ(べし)む人の娘などは、差し交じはらせ…
(4)そのころ院の賭弓あ(べし)。
問四 c「金は~しかざるがごとし」について、「金」「鉄」がそれぞれ何の道の例えとなっているか明らかにして、この部分を口語訳せよ。
模 範 解 答
問一 a 当然 終止形 b 可能 未然形
問二 (1)
問三 (1)べけれ (2)べき (3)べから (4)べし
問四 金(幽玄の道)は鉄(文・武・医の道)よりも優れているが、鉄の用途の多いのに及ばないのと同じだ。