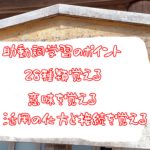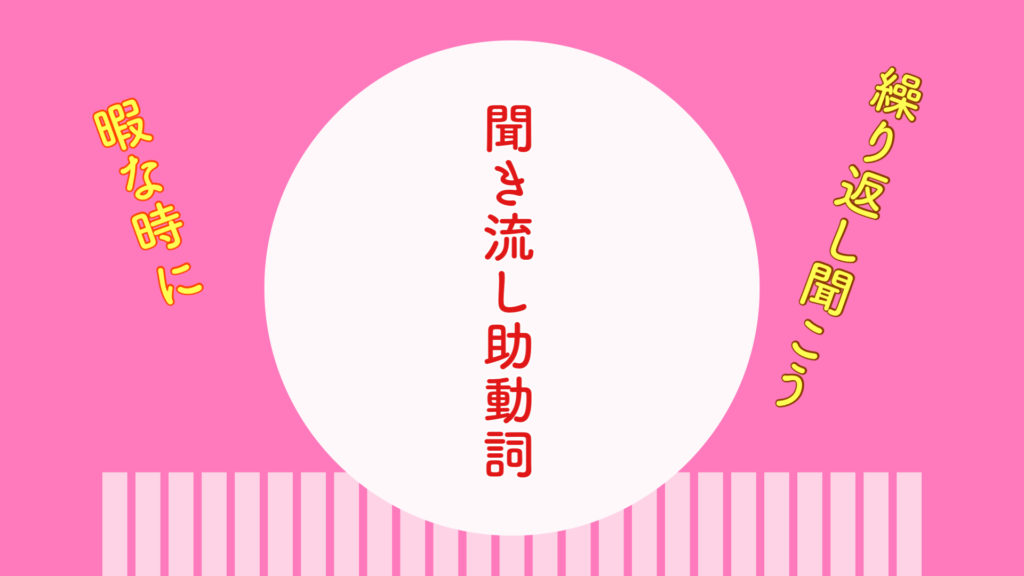本 文
あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山の烟立ち去らでのみ住み果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからん。世は定めなきこそいみじけれ。
命あるものを見るに、人ばかり久しきはなし。かげろふの夕べを待ち、夏の蝉の春秋を知らぬもあるぞかし。つくづくと一年を暮すほどだにも、こよなうのどけしや。飽か ず、惜しと思はば、千年を過すとも、一夜の夢の心地こそせめ。住み果てぬ世にみにくき姿を待ち得て、何かはせん。命長ければ辱多し。長くとも、四十に足らぬほどにて死なんこそ、めやすかる べけれ。
そのほど過ぎぬれば、かたちを恥づる心もなく、人に出で交らはん事を思ひ、夕べの陽に子孫を愛して、さかゆく末を見んまでの命をあらまし、ひたすら世を貪る心のみ深く、もののあはれも知らずなりゆくなん、あさましき。
口語訳
あだし野の露が消えることなく、鳥部山の煙が立ち去らないだけで住み続ける習慣があるなら、どれほど物の哀れもないだろう。世の中は不確かなものだからこそ悲しい。
命あるものを見と、人だけが長生きするわけではない。かげろうのように夕方を待たず(死に)、夏の蝉のように春や秋を知らない生き物もいる。しみじみと一年を暮らせば、豊かな時間が過ぎていくのだ。(逆に)命を惜しいと思って生きていると千年生きても短いと思うだろう。永遠には生きられない世の中に、長生きした末に醜い姿を得て、それが何になるだろう。命が長ければ、恥も多い。長生きするとしても、せいぜい四十年ほどで死ぬのが見苦しくない。
それぐらいの年齢(四十歳)を過ぎると、醜い容貌を恥じる気持ちも無くなり、人に交わることを欲して、老いさらばえて子孫を愛して、子孫が立身出世する末を見届けるまでは生きよう、などと期待し、ひたすら世をむさぼる心ばかり深く、もののあはれもわからなくなっていく。あさましいことだ。
助 詞
アクティブラーニング
・今回も実際の授業を想定しています
○最初に接続助詞の説明をする(20分)
「ば」順接の仮定条件・順接の確定条件(原因・理由、偶然、恒常もしくは恒時条件)
↓
生徒たちに練習問題を解かせる
○インプットの練習
範読してペアで音読させ
『あだし野の露消ゆるときなく』のプリントから接続助詞を探させます
(個人で探す:ここはじっくりでいいと思います)
(生徒はすぐに答えを聞きたがるので「数だけは教えるよ」と言ってもいいかもしれません)
↓
○次にアウトプットの練習に入る(ペアで内容を確認)10分
↓
○全体に向け正解の確認と文法などの説明:10分
接続助詞は10個です
「が」「に」「を」の説明を工夫します
・特に「単純接続」と「順接」の違いは微妙です
・「の」「に」の上の部分が下の条件となっていれば「順接」だといえば安心します
・実際は「~。そして…」と置き換えた方がいいと私は思います
↓
○次にプリントから係助詞と格助詞を抜き出します(25分)
(ここはペアもしくはグループで取り組ませるのがいいと思います)
↓
○係助詞は13個です(20分)
「は」「も」に気づきませんのでヒントをだしてあげました
↓
○格助詞は28個あります
まとめ(5分)
○助詞をみつけるのは大変だけど一度やるとコツが分かる
○それぞれの助詞がどれなのか考えられるようになる
○問題を解く時もこれがきっと役に立つ
と伝えます
参 考

生徒にやる気をださせるという観点からも授業前に「学習目的」を伝えることは大事なことです。古文編でも書きましたが文科省の調査でそのことが報告されています。生徒はアクティブラーニングの意味を正確に理解できないと遊びの時間と感じてしまうことになります。そこを怠ると授業が崩壊してしまうこともあります。さらに意図がうまく生徒たちに伝わらない授業をすると生徒たちだけでなく保護者やほかの教員にまで誤解されるおそれも出てくるのです。また、先生たちが積極的にアクティブラーニングを積極的にできない原因として実際の教育現場とかけ離れた事情があります。成績のいい生徒たちを相手にならできるけれど教室にいてを受けさせることが目的の学校の場合、どうやってアクティブラーニングを実施すればいいのか、文科省の指示だけではできないと考えている先生は多いです。そこでここに試案を示します。参考になれば幸いです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||